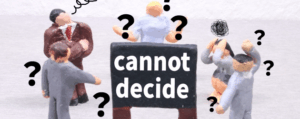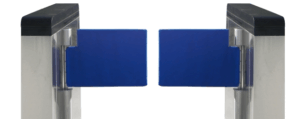No.53: まずアラームを上げているか?|プロジェクトの進め方

プロジェクトにおいてタスクを消化していると、予想していなかった問題が生じることがあります。多くは担当者が自分で解決できる問題かも知れませんが、思った様に解決できず問題が長引いてしまうと、後続のタスクや他者のタスクに、そしてプロジェクト全体の進捗に影響を与えてしまうことにもなりかねません。問題に直面した時には、まずプロジェクトマネージャ(PM)に、またはプロジェクト内にアラームを上げているでしょうか?
担当者の立場としては、自分のタスク内の問題だから自力で解決するのが自分の責任だと思うことでしょう。その姿勢は非難されるものではありませんが、チームで目標の達成をめざすプロジェクトにおいて、一時的にでも個人で問題を抱えてしまうのはリスクであるという認識を共有しなければなりません。自分の責任を全うしようとして、プロジェクトが負っている責任を全うできなくしてしまうのでは本末転倒です。
担当者がしなければならないことは、問題を見つけたらその場で解決に要しそうな時間と解決しなかった場合の影響度を合わせて問題の重要度を評価し、少しでも重要度が高いと判断したらすぐにアラームを上げることです。まずアラームを上げ組織内で状況を共有したうえで問題に対処することです。言葉にすると面倒そうですが、一部の人は自然にやっていることと思います。
解決に要しそうな時間については、明確な解決策があったとしても、その実行に時間を要する場合は過小評価できません。一方すぐに解決策が浮かばずやってみなければわからない場合でも、トライ&エラーにそれほど時間を要しないと予想できれば一旦問題は小さいと考えて良いでしょう。ただし、やってみたら意外にすぐに解決せずに、それを繰り返してしまう様になれば問題は大きいものと捉え直す必要があります。この一旦小さいと評価した問題の大きさを捉え直すのは、難しいことだと認識しなければなりません。トライ&エラーに熱中してしまうと一旦立ち止まるのを忘れ、そのまま突き進み続けてしまいがちだからです。
また、解決しなかった場合の影響度については、プロジェクトに与える影響が甚大な場合、すぐに解決できそうと考えても軽視してはいけません。自身のタスクが遅れるだけでなく、他者のタスクやプロジェクト全体に影響を及ぼす様な場合は、その解決策も共有すべきだからです。場合によっては他者がより良い解決策を持っているかも知れません。
以上の解決に要しそうな時間と解決しなかった場合の影響度を掛け合わせ、問題の重要度を判断し、重要度が高いと思ったらその場でアラームを上げる必要があります。重要度の捉え方は個人によって異なるでしょうが、迷った場合はアラームを上げる対象とすべきです。
そしてここが重要なところですが、担当者がアラームを上げるのを躊躇してしまうことの無いようにしなければなりません。アラームを上げるとPMや管理者が過剰に反応し、状況を短い周期でフォローしたり、担当者の作業に介入するようであると、担当者はその様な負担を避けたいと思うに違いありません。また、組織が問題に向かわず人を非難・叱責する様な風土であると、担当者の価値判断の基準が怒られないことになってしまい、問題を隠しがちになります。アラームが上がらず問題の共有が遅れ、組織として手を打てないままプロジェクトに影響を及ぼしてしまうことが散見される場合は、組織の風土についても考えてみる必要がありそうです。
なお、担当者の行動としては、問題のアラームを上げる時にそれに対する対策予定もセットで示すことで、過剰な反応を抑えるようにすることが求められます。
あなたのプロジェクトや組織では、担当者からまずアラームが上がりますか?それを妨げる様な風土になっていませんか?
関連提言:No.38: そこに隠蔽はないか