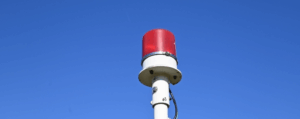No.54: フェーズゲートを設けているか?|プロジェクトの進め方
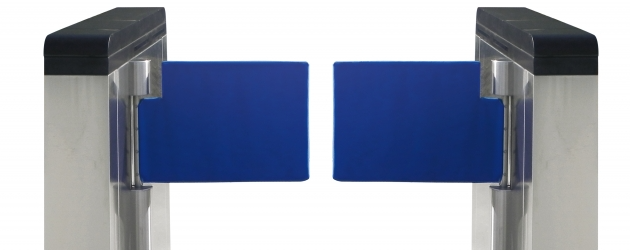
新製品の開発プロジェクトで計画に従ってタスクを消化していく。オンスケで順調に進捗している様に見える。しかし、プロジェクトの終盤になっていくつかの懸案事項が未解決のまま残っている。しかも、本来なら上流工程で解決しておかなければならない懸案だったので、これから後戻りが発生してしまう可能性が高い。成果目標の品質についても当初の想定以上に多くの問題が見つかっている・・・。
経営者としては、プロジェクトの終盤になってこの様な状況を見せられてはたまりません。開発プロセスは確立しておりそれに従って作業が進められていた”はず”なのに、と思っても後の祭りです。
結局実行するのは人間なので、”人”に依存する部分は残ってしまいます。PMがプロジェクトの前半は目に見えづらい品質より工程の消化に目を向けてしまい、品質は検証段階で確認して高めていけば良いと考えてしまうことは往々にしてあります。懸案事項が残っていることは認識していても、誰にやらせれば良いかわからないまま目の前の業務に目を奪われて先送りしてしまうこともあります。
だからと言って”人”の意識や行動に依存した部分をそのままにしてしまっては、プロジェクトを安定して成功させていくことはできないでしょう。作業の積み残しや見逃しをチェックし手を打てる仕掛けが必要です。それがフェーズゲートです。
開発プロジェクトの設計フェーズが終わった時点で、設計レビューの指摘事項はすべて刈り取れたか。懸案事項のうち設計フェーズ内で対策しておくべきものは漏れなく完了できたか。他に組織として予め定めたチェックポイントも含めて、すべてクリアできたことを確認して設計フェーズを完了する、そして次のフェーズに向かってゲートをオープンする、ということを第三者が判定する仕掛けを設けておくのです。設計フェーズに限りません。ゲートは、組織が定義した開発プロセスに合わせ、区切りの良いところに複数設けます。それぞれのフェーズでやるべきことが計画通り終わったことを確認して次のフェーズに進むということを積み重ねていくのです。
フェーズゲートを設けておくことによって、本来そのフェーズで解決しておくべき問題が放置され、先送りされたままプロジェクトが進んでしまい、終盤になってから一斉に品質や工程の問題が噴出するという事態を避けることができます。
皆さんの組織のプロジェクトには、フェーズゲートが設定されているでしょうか?ゲートをオープンする条件は適切に定められ、PMがやることもやらずに先を急いでしまう状況を防止できているでしょうか?