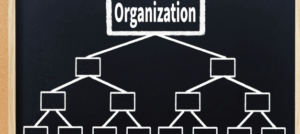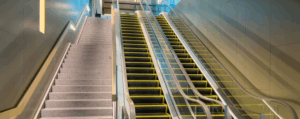No.58: その仕組みはほんとうに機能しているか?|プロジェクトマネージメントのあるべき姿

我が社では開発プロセスが決められているし、プロジェクトを進めるに当たっての規準やルールも決められ、それに従って運用されている。経営者のあなたはこの様に思っているでしょうか。もし文字通りだとすれば、あらためて現場に足を踏み入れて実態を点検した方が良さそうです。
引っ掛け問題の様で恐縮ですが、前述の「開発プロセスが決められている」、「規準やルールも決められ」そして「運用されている」という言葉はすべて受け身です。どこかに、人任せの部分が見え隠れしています。企業や組織を率いる立場の人であれば、自らを主語とし、「開発プロセスを決めている」、「規準やルールも決めている」そして「それに従って運用している」と言って欲しいところです。
というのも、「されている」という表現には事実を自分の目で確認しておらず、願望や伝聞が滲み出ており、主体性が感じられないからです。
開発プロセスやプロジェクトの規準・ルールを定め、その適用を始めたことで安心してしまっていないでしょうか。適用を開始して完了ではなく、これからのプロセスの不断の改善活動が始まりだということを、どれだけの方が認識しているでしょうか。
そんなことは判っている、我が社では規準・ルールが守られているか、定期的にチェックする活動を行っているし、規準・ルールに不備があればそれを改訂する委員会も設置している。と、そう言いたい方もいるでしょう。
さて、それらの活動はおざなりにはなっていないでしょうか。
規準・ルールに沿った仕事が行われているか、品質管理部門やPMOの様な部門が組織内で内部監査の様なことを行い、杓子定規に各部門の遵守状況を評価して幹部会議に報告する。規準・ルールが守られていない部門は幹部会議を通して叱責を受け、次回から同じ指摘を受けないように、”指摘を受けない様に作業”をする。組織全体的に遵守状況が悪いと品質管理部門の様なところが叱責を受けてしまうので、内部監査に手心を加える。
そこにはなぜその規準・ルールがあるのか、そしてその部門はなぜそれを守らなかったのか、もしかして現場はその規準・ルールが自分たちの仕事にとって有効であると思っていなかったのではないか、といった本質的な議論が忘れられています。結果、組織は徐々に規準・ルールを守るということにフォーカスを当てる、指摘を受けない様に監査報告をまとめるということに注力する、いわゆる”手段の目的化”に感染していくのです。
本来は、規準・ルールが守られていない状況を発見したら、それは組織が仕組みを見直す好機と捉えるべきなのです。規準・ルールに過剰に重くなってしまっているところがないか、組織内でそれに変わるもっと良いやり方を運用していたのではないか、ルールを守る以前に当該組織の規律が乱れてしまっているのではないか、といったことを前向きに掘り起こしていった方が、叱責して強制的に是正するよりも長期的には有効だと思いませんか。
大組織の経営者の皆さんの場合は、直接現場に入って何が起きているのか確認するのは難しいかも知れません。そのときは、自分に変わって冷静かつ客観的に現場を見ることができる人材に権限委譲すれば良いのです。ただし他人に任せるとしても、あくまで責任は自身にあって「決めている」「運用している」と一人称で語れる姿勢が欲しいところです。 如何でしょうか。あなたの組織では仕組みが機能しているでしょうか?それを不断に見直す努力が行われているでしょうか?
関連提言:No.44: プロセスが確立されているか