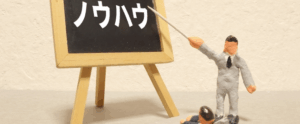No.64: 千慮の一失を避けるために|プロジェクトマネージメントのあるべき姿

自分が顧客のことを一番わかっている、自分がこの技術について一番詳しく知っている、自分が社内で一番経験がある。そういった自信を持っている設計者やプロジェクトマネージャー(PM)にとってみれば、レビューというイベントはただの通過ポイントに過ぎず、不要なイベントと思えるのかも知れません。
開発プロジェクトにおいて、計画、設計、製作、検証等の各フェーズで、第三者を交えたレビューにより手戻りを防止する活動は欠かせないものです。しかし、自称も含めて優秀な設計者やPMが、レビューで指摘される様な問題や誤りは作り込んでい(るはずが)ないので、やる意味がないと考えてしまってはどうなるでしょうか。
レビューの場では、設計者が考え方や設計内容の説明をするだけでレビューアからそれらに対する指摘がない。指摘があっても、内容はどうでも良い文言に対する指摘や資料の体裁に関すること。場合によっては、設計者が詳しい技術に関する勉強会になってしまう・・・。
この様なことになってしまっては、設計者やPMがレビューを単なる通過点と考えてしまうのもやむを得ません。そんな非生産的なレビューとなってしまうのを避けるにはどうすればよいでしょうか。
レビューが効果を発揮するかどうかは、レビューアとして誰が参加するかにも依存します。確かに、顧客のことを、顧客の要求内容を、そしてそれを実現する技術について一番よく知っているのはプロジェクトの当事者かも知れませんし、そうであって欲しいものです。だからと言ってそれ以外の者が何も本質的なことを指摘できないかというとそんなことはありません。
そのプロジェクトについてよく知らなくとも、顧客の要求内容の消化の仕方、それを設計に落としていくプロセス等、レイヤーを上げて、つまり俯瞰してプロジェクトの進め方、設計思想をチェックすることはできるのです。
「千慮の一失」という言葉があります。どんなに賢い人でもたくさん考えたことの中には一つぐらい間違いや勘違いがあるということを指します。プロジェクトの中身を知らなくとも、当事者の考え方をよく聞き、少しでも疑問や不審に思った点を深掘りし、質問を重ねていくと、設計者が深慮なしに、思い込みで進めたところが見つかったりします。結果的にそれは正しい判断だったかも知れませんが、後々の検証ポイントとして識別することができるだけでも十分にレビューの成果となります。
もし設計者やPMの上司にプロジェクトを指導できる知識や力量が備わっていないならば、それを認めたうえでその上司は組織内、企業内で最適な有識者に参加してもらうべきです。
組織、企業の中で最善のメンバに参加してもらう限りにおいて、それは組織、企業の力が試される場となります。それでもレビューが効果的にならないのであれば、それはその時点の組織、企業の実力であるのだから仕方がありません。実力が足りないのを認め、徐々に経験を積み上げていけばよいのです。避けなければならないのは、「千慮の一失」を見つけるための努力をハナから放棄してしまうことです。そして、逆に、何か指摘しなければならないと考えて、本質から外れた思い付きのアイデアを捻り出して現場に無駄な消耗をさせてしまうことです。
如何でしょうか。あなたの組織では、優秀な設計者やPMが担当しているプロジェクトでも、「千慮の一失」を見つけようとしているでしょうか。そしてそれは適切に実行されているでしょうか。