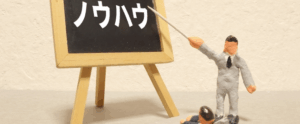No.66: 役割と責任範囲は明確か|プロジェクトマネージメントのあるべき姿

新しいプロジェクトを始めるときに、プロジェクトメンバがどこから集められるかは当然ながら重要なポイントです。メンバはその出処の部門において、それぞれ異なる役割と責任範囲を経験してきています。新たなプロジェクトを始めるときには、その染みついた役割と責任範囲をオーバーライドする必要があります。
プロジェクトの規模が小さく、体制が同じ部門のメンバで構成される場合や、これまでも同じメンバでプロジェクトを経験してきた場合は、それぞれの役割と責任範囲が特に明文化されていなくとも暗黙的に引き継がれ、業務に支障は生じないかも知れません。
しかし、プロジェクトの規模が大きく、これまで一緒に業務をしたことがない部門やメンバを含んだ体制となる場合、役割と責任範囲をそれぞれのそれまでの経験に任せてしまうと、混乱を招く可能性が高くなります。
必要な連絡や指示が伝わらない。情報が共有されない。コミュニケーションの抜け漏れや滞りは、プロジェクトにとって致命傷です。また、複数のメンバが同じ作業を重複して実施してしまう。誰も手を付けない作業が発生してしまう。これらはいずれも後で発覚したときには、計画を揺るがす事態を招くでしょう。
プロジェクトマネージャー(PM)は、プロジェクトの計画段階でWBS(Work Breakdown Structure)に基づいた工程計画を立てますが、そこに記載されるタスクはその完了条件と成果物が定義されるものの、他のタスクとの境界に曖昧な部分が存在してしまうものです。そういった部分は、事前に各自の役割と責任範囲を明確にしておくことによって極小化できます。
WBSを徹底的に細分化し、その中でタスクの作業内容を事細かに定義するという方法もあるでしょう。しかしながら、それは現実的ではありません。各メンバは複数のタスクを担当することになるので、役割と責任範囲はメンバ毎に、あるいは設計者、プログラマといった抽象的な立場に対して明確にした方がより現実的でわかりやすいものになります。
これまでと同じメンバで進めるプロジェクトにおいても、役割と責任範囲については一度振り返り、点検してみることをお勧めします。うちのチームはうまく行っていると思っているのは管理者やPMだけで、現場では実は曖昧な部分を一部の気の利いたメンバによってカバーされていることがあるかも知れません。
体制から一人抜けたら、今まで順調に消化されていたプロジェクトや業務において途端に問題が発生するようになった、ということがないでしょうか。それは明確にされていなかった役割が隠れていたということに他なりません。
プロジェクトを円滑に進めていくために、重要なチームビルティングの一つです。メンバの役割と責任範囲を曖昧なプロジェクトでは、曖昧に仕事が進められ、結果として曖昧な成果物しか生まれません。あなたの目の前のプロジェクトの成果物はどうなりそうでしょうか。