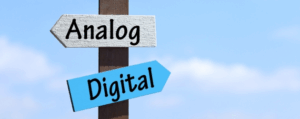No.71: アラームに対して適切に対応しているか|プロジェクトマネージメントのあるべき姿

プロジェクト内でアラームが上がって来た場合、どの様に対応しているでしょうか。よもや、「頑張れ」「何とかしろ」と精神論で押し返し、放置してしまってはいないでしょうか。そこまでストレートな反応でなくとも、結果的には放置してしまうのと変わらない対応により、気がついた時には大きく炎上してしまっていたということになっては後の祭りです。
プロジェクトマネージャ(PM)であればプロジェクトの担当者から、PMの上司であればPMから、さらに経営幹部であればPM、PMの上司または企業内でプロジェクトを横断的に監視している部門から、アラームが上がった時にどの様に対応しているか。ここでの初動は、以降のプロジェクトの着地に大きく左右します。
まず忘れてはならないスタンスは、アラームを上げてくれたことに感謝することです。「報告(相談)してくれてありがとう」と言葉にできるに越したことはありませんが、少なくとも対応にポジティブな姿勢を見せるのが大事です。
ここでネガティブな対応、ましてや叱責や落胆から入ってしまう様では、次回以降アラームを上げるべき局面で躊躇させてしまうことになり、これは組織内に伝染して問題を隠すという風土・文化がひっそりと育っていきかねません。
そして、アラームを受け取った者がすることは、その重要度を仮に評価し、組織内でのエスカレーションの度合いを判断することです。受け取った者が無条件にさらに上位者にアラームを伝搬させては、企業内のアラームがすべて社長に上がるということになってしまいます。
そして、アラームを上位者に伝えるとしても、そのアラームに対する対処は自分が行うということを付け加える必要があります。「○○プロジェクトで△△の様な問題が発生しており、私がこれから詳細確認し対処します。」という様な感じです。
この報告を受け取った上位者は、同様に重要度と組織内でのエスカレーションの度合いを判断することになりますが、自分もアラームに対処するという無駄なアクションは避けられます。そして、アラームに対処している状況や結果について都度報告を受け、重要度に変化がないかに注意するだけでよくなります。
なお、初めに”重要度を仮に評価”と言ったのは、アラームの初報だけでは重要度を正しく評価することはできないためです。アラームの元となった”事実”を自ら確認していく過程で、当初考えていた状況より深刻な状況であったり、すぐ解決できるものであれば、その重要度は見直されることになります。
例えアラームが、大きな問題に繋がるものでなかったり、勘違いによるものだったとしても、絶対にそれを非難しないことです。その理由はもうお分かりのはずです。もしかしたら大きな問題になるかも知れない状態でまず一報を上げるのは、組織として健全な状態です。
ここで、ダメな組織は、アラームがそのまま報告として上位層までリレーされ続け、誰も対処しないというもの。あるいは、アラームに対して複数の階層がそれぞれ別々に口出しし逆に現場を混乱させるというものです。
これは、組織における責任と権限が不明確であることによって発生するものです。
さて、あなたの組織では、部下からアラームが上がってきたら、どの様に対処されていますか。放置されていませんか。頑張れと押し返されてしまっていませんか。上位者にリレーされているだけではありませんか。適切に対処されているでしょうか。