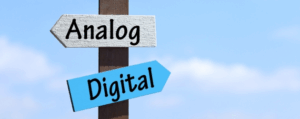No.73: 現実をT型に把握する|プロジェクトマネージメントのあるべき姿

プロジェクトを遂行するときにプロジェクトマネージャ(PM)がどの程度現場に入り込むかというのは、プロジェクト管理において常についてまわる疑問であり問題です。管理業務だけを行なっていては現場で起きている問題に気がつくのが遅れてしまうかも知れないし、現場に入り込みすぎてはPMに負荷が集中しプロジェクト全体に目配りできない事態になってしまうかも知れません。
少人数のプロジェクトであれば、PMがプレーイングマネージャとして現場の業務も担当することがあるでしょう。
一方、大人数のプロジェクトで、体制が複数のチームで構成されている様な場合、PMが全体の管理をしながら現場に入り込む時間には限りがあります。
そういったときに有効なのは、現場で起きている現実を”T型”に把握するということです。
例えば開発プロジェクトにおいて、機能A、機能B及び機能Cを実装する必要があり、それぞれの開発ステップとして要求分析、設計、制作及びテストがあるとします。そこで、一番肝となる機能または実行チームに不安のある機能に対して、各開発ステップをできるだけ伴走するのです。具体的には、都合のつく範囲でチーム内のミーティングやレビューに参加する、チーム内で行われているドキュメントチェックの記録を確認してみるということです。
その機能を担当しているチームのリーダと同じレベルの関与はもちろんできません。しかしながら、例えば実施されたドキュメントチェックの結果を眺めてみれば、表層的な誤字脱字の指摘に終始せず、設計内容の本質的な指摘や修正が行われているかが分かります。そして、指摘項目のうち気になるものがあれば一つだけでも、なぜそう考えたのか、チームリーダ及び担当者の思考過程を深掘りするのです。
まさしく”深掘り”を進めると、ピンポイントの問題だけでなく、否応でも周辺の状態が視野に入ってくるものです。それは、小さな穴を掘り始めても、深く掘り続けると穴が大きくなっていくことと同じです。そうやって一つの機能の進み具合、出来具合についての現実を把握していきます。
そして一方、その他の機能については、同様な粒度で確認を行うことはできないでしょう。そこでできることは、深掘りした一つの機能において、機能固有のもの以外で気がついた注意点やポイントについて確認することです。そういった注意点やポイントが、他の機能においても適切に対応されているかどうかを確認するだけでも、全体的に状況が大きく逸脱していないかどうかというおおよその判断ができます。
つまり、全体を薄く満遍なくカバーしながら一部に対しては深く掘り下げる、T型に現実を確認するということです。T型のセンサーのどこかで引っ掛かれば処置を行い、もしこのセンターに引っ掛からない問題が潜在していれば顕在化した時点で処置します。そういった割り切りも大切です。
これは、PMがプロジェクト内の実態を確認する方法でもありますが、プロジェクト外の第三者、例えばプロジェクトから発信されたアラームを受け、まず現実を把握しようとする上位管理者にも適用できる方法です。
如何でしょうか。あなたはプロジェクトの実態をどの様に把握していますか。担当者並みに現場に入り浸りでしょうか。会議室で報告を受けるだけでしょうか。それとも。。