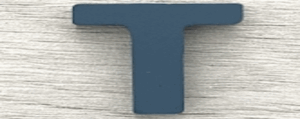No.74: その遅れは挽回できるのか|プロジェクトマネージメントのあるべき姿

工程会議や日々のミーティング等で、各タスクの進捗を確認したところ遅延が見つかるのは、プロジェクトを進めているうえでは当たり前に発生することです。さて、その遅延に対してどの様に対処しているでしょうか。担当者からの「○日遅れているが、△日までには挽回します」という返答を鵜呑みにして終わらせてしまっていないでしょうか。
プロジェクトマネージャ(PM)に対してプロジェクト内のメンバから、あるいはPMの上司に対してPMから遅延のアラームが上がったときに、初動を誤ると後々のプロジェクトの進行にN倍の影響を与えかねません。適切に対応するために、まず現場や現物を自分の目で見て現実を把握すること、そしてその把握は定性的にとどまらず定量的に、デジタルに行うべきであることは、これまでも述べてきた通りです。
現実を把握したうえで、次のステップはその遅延にどの様に対処するかということになります。ここでも、挽回策を定性的なものにとどめず、定量的な根拠を持ったものとする必要があります。決して”根性論”で挽回させてはいけないし、そうすることを認めてはいけません。
私の経験から、この様な状況でよく聞かれる挽回策は、残業でカバーするというものです。一言で”残業でカバーする”といっても、その背景によって妥当性は異なります。
まず、そもそも当初の計画が、これはお勧めできませんが、毎日の残業を前提とした日程となっていれば、遅延を残業でカバーすることは不可能です。
毎日21 時まで仕事する前提だったところ、24時までやろうとでもいうのでしょうか。初めから21時までやることを前提に1日の仕事を始めるのと、24時までやることを前提に始めるのとでは、結果的に得られる成果は変わらないものです。それは、初めから定時退勤時間である18時までを前提に始めても、変わらなかったりするのです。同じアウトプットを、凝縮した時間で生み出すか、薄めた時間で生み出すかの違いです。
ここで、一度振り返ってみて欲しいところとして、計画における1日とは何時間を表すものかということです。1日を8時間と見るのか、余裕時間を考慮して7時間と見るのか、はたまた残業前提の12時間と見るのかによって大きな違いがあります。そもそも1日を何時間かということも考えずに日程を計画しているプロジェクトもあります。メンバに心身共に健康な状態で仕事をしてもらうこと、ブラック企業の誹りを避けることからも、残業を前提としない時間とするべきですが、そういった話を別にしても1日とは何時間なのかということをプロジェクト内で明確にしておく必要があります。
次に、当初の計画が1日の作業時間を残業抜きに考えているものだとして、だから遅れた分を残業によって補うという考え方ですが、これは遅れた原因が何らかの理由により当初計画した時間を確保できなかったことによるものというのであれば妥当性があります。
しかし、例えば全体で7時間x 5日 = 35時間と見積もったタスクにおいて、3日(= 21時間)経過した時点で進捗が30%であれば、時間と進捗が比例すると仮定すると全体では21時間÷0.3 = 70時間必要だったということになり、さらに後(70 – 21 =)49時間要するということになります。これは残業でカバーできる範囲を超えているものと言えるでしょう。
ここで、この遅れの原因は単に計画時の作業量または作業効率の見誤りによるもので、時間さえあればタスクを完了できるというケースであれば、まだ理解できます。しかし大事なポイントとして、遅れの原因にインプットの問題、技術的な問題等、時間によって解決できない要素が含まれていた場合は、大きく判断を誤ります。
つまり、そういった背景、根本的な遅れの原因を踏まえたうえで、”残業でカバーする”といった様な時間があれば完了できる状況なのかどうかを判断する必要があるのです。
私の経験上、挽回策として”残業でカバーする”と聞いたものほとんどは、遅延の原因を掘り上げていくと、決して時間だけの問題ではなかったということを付け加えておきます。
あなたの足元のプロジェクトにおいて、発生している遅れへの挽回策はどの様なものになっていますか。それはほんとうに挽回できるものになっているでしょうか。
関連提言:No.49: その工程会議は効果的か?