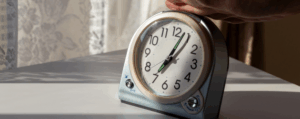No.70: 検査部門を当てにしてしまっていないか|プロジェクトマネージメントのあるべき姿

プロジェクトの実行に関わる組織は、当然ですが企業によって異なります。開発プロジェクトに対して、企業によっては設計、製作を実行する部門の他に、製作したものを検査する部門が存在するところもあります。企業としては、設計、製作されたものの品質をどの様に担保するか、そこにおける検査部門の関わり方にはしっかりした理念が必要です。
さて、あなたの企業において、設計者が自分達の作ったもののテストを、検査部門に依存してしまっている様なことはないでしょうか。
私が企業の現場で駆け出しの設計者だった頃、先輩から「検査(員)に不良を指摘されるのは設計者として恥と思え」と指導されました。自分が設計したものの出来栄えは、しっかり自分でテストして、不良は取り払い完璧な状態にして検査工程に引き渡すべし、ということです。
いわゆる”製品”を市場に出すまでの工程において、それぞれの担当工程において自分の作業責任を果たすということに他なりません。こうすると当たり前の様に聞こえますが、これがソフトウェア開発の話になると必ずしもそう考えられていない世界に出逢います。
まず、そもそもソフトウェアに対する検査部門を設けていない組織もあります。ソフトウェアに限らず製品を扱ってきた経緯からソフトウェアも工場で生産する様な製品の一つと捉えて、疑いなく検査部門を設けている企業がある一方、ベンチャーとして少人数でスタートし専門の検査部門を設けないまま成長してきた企業もあります。
そういった企業では、設計者自身がテストする、あるいは専任のチームがテストして製品を出荷するということが行われます。この段階では、まだ設計者も自分の作ったものを自分達で検証し、完璧な(と思える)ものを出荷しようという意識を持っているでしょう。
しかし、企業が成長し検査部門を創設した途端に、テストチームのノリでテストや検証を検査部門に委ねてしまうことが起き得ます。あるいは、当初はその様な役割でなくとも、それを理解していない設計者、不遜な設計者が自分が作ったもののバグ出し(ソフトウェア上の不良摘出)を検査員の役割と思って自身の責任をまっとうしないことになり得ます。
この様な設計者を正す手段として、または設計品質を向上させる手段として、検査工程で不良が検出されたら、当該製品を設計者に差し戻し、設計者はその5倍、10倍の新たな不良を見つけてからでないと再び検査工程に進めない、いわゆる「5倍返し」「10倍返し」という荒療治も経験したことがあります。
検査部門は、製品が仕様通り、あるいは顧客の要求通りに動作することを確認するところで、設計者の尻拭いをするところではありません。検査部門が設計者の補完作業をしてしまうと、設計者とは違った観点で検査するという本来の役割を果たせないことになりかねません。
もちろん、設計者としては不良が残っていないと自信を持った状態で検査工程に送ったにも関わらず、検査によって不良が見つかることはあります。その様な時は、設計者が見つけられなかった不良を見つけてくれた優秀な検査員に感謝しなければなりません。
私が所属していた企業では、当初は検査部門という呼び方だったのもの、途中からは品質保証部門として、製品の検証だけでなく顧客に対して文字通り品質を保証するという位置付けが明確になりました。品質保証部門にとってみれば、製品の検査はその責務の一部に過ぎず、設計者がたどった業務プロセス、設計の妥当性、検証の妥当性、そして設計から検証までのトレーサビリティをトータルで確認したうえで、自信を持てる状態で製品の出荷を判定するというより大きな責務を担う様になったのです。
その様な部門に設計者が自身の尻拭いをさせてしまって良い訳はありません。
あなたの組織では、設計者が自分の作業、成果物に対する責任を果たしているでしょうか。検査部門、品質保証部門に設計者の補完業務をさせてしまっているということはないでしょうか。