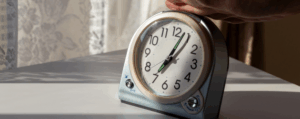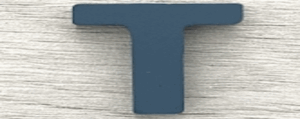No.72: 現実をデジタルに把握しているか|プロジェクトマネージメントのあるべき姿

前回、プロジェクト内でアラームが上がった時に適切に対応しているかという話をしました。適切に対応するには、まず現実を把握することです。つまり、プロジェクトの現場がどの様な状況にあるのかを正確に認識するのです。
状況を正確に認識するには、自ら現場に足を踏み入れることはもちろんですが、現場の状況を定性的だけでなく定量的に見なければなりません。元々プロジェクトの状況が定量的に管理されていなかったとしたら、まずそれ自体が根本的な問題であり、遅まきながらそこからでも物事を定量的に測る仕組みを取り入れる必要があります。状況を正確に把握するまでに多少時間を要することになりますが、それなしに問題に効果的に対処することはできません。
そんなことにならない様、日頃からプロジェクトを定量的に、デジタルに管理する仕組みを取り入れておかなければなりません。アラームが上がる事態になろうとなるまいと、プロジェクト内の状況をデジタルに管理せずに、プロジェクトを成功に導くのは難しいと言えます。
デジタルに管理するとはどういうことでしょうか。
品質面に関して言えば、プロジェクト終了時、何を持って必要とする品質を確保したと宣言できるのでしょうか。開発プロジェクトの場合、単に制作したものの試験を実施して不具合が見つからなかったというだけでは誰も納得させられません。
ソフトウェアの品質であればテストでソースコードの全体を動作させているか、いわゆるカバレッジは100%達成しているか。そのうえで、プロジェクトでソースコードの単位ステップ数あたりのテスト件数、いわゆるテスト密度を定め、それを達成しているか。さらに単位ステップ数あたりの不具合件数、いわゆるバグ密度が目標に対してどうなっているか。
これらデジタルで管理されたデータを元に、品質面でテストが不足しているところ、不具合が多発しており品質向上のための見直しが必要なところを現実として把握するのです。
工程面に関して言えば、計画に対して10日ぐらい遅れており、今後遅れが拡大する見込みという報告があったときに、10日遅れの実態と今後の見通しを定量的に把握します。
単に”10日遅れ”と言っても、それは1人が担当しているタスクが10日遅れ、つまり10人・日遅れているのか、それとも2人で担当しているタスクが10日遅れ、つまり20人・日遅れているのかでは大きな違いがあります。さらに、そのタスクの終了を待っている後続のタスクが複数あり、それらに多くの人数が関わる計画であったとすると、潜在的な遅れはより大きいものとなります。
まずこれらをデジタルで浮かび上がらせるのが、現実を把握する第一歩です。それをせずに、プロジェクトを冷静に進めていくことは不可能ということがわかっていただけると思います。
あなたの目の前のプロジェクトは、状況をデジタルで管理できていますか。アラームが上がった時に、すぐに現実を定量的に把握できるでしょうか。